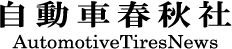天然ゴムは“高強力”“耐摩耗”“低燃費”といった特性を持つタイヤ原材料の一つ。その使用量はタイヤ用の原材料重量全体の約25%を占め、タイヤを支える部材や、鉱山用、トラック・バス用タイヤのトレッドなど耐久性が求められる部分で多く使用されている。タイヤにとって重要な天然ゴム資源に関し、どのような研究が進められているのか――ブリヂストンの取り組みを、先端材料部門長の大月正珠氏と同部門天然ゴム技術研究課長の中川大助氏に聞いた。
拡充、多様化を柱に研究を
天然ゴムの優れた特徴は、引っ張ると質の良い結晶が合成ゴムに比べて生じ易い点にある。実際にタイヤが路面に接地して離れる場面では、ゴムが引っ張られる方向の歪みによって部分的に結晶が生じ、その結晶が丈夫さを生み出す。大月氏によると「この特徴を人工的に作ることは非常に難しい」という。

タイヤにとって欠かせない天然ゴム――そもそも植物由来のため再生可能資源であるものの、ブリヂストンではそのサステナブル(持続可能)化に注力している。この背景について中川氏は「将来、世界人口が増え、その移動手段となる自動車の台数も増加すると予想されている。タイヤの需要が増えれば天然ゴムの需要増加も見込まれる」と説明。さらに、天然ゴム供給源であるパラゴムノキの生産地が東南アジアに集中していることから、病害などによる生産リスクの緩和も求められているそうだ。
これらの観点から同社は天然ゴム資源のサステナブル化を重要課題と捉え、“拡充”“多様化”を柱に技術開発を推進している。
“拡充”ではAI(人工知能)による画像診断を活用したパラゴムノキの病害診断技術を開発。ドローンによる空撮画像から根白腐病の有無をAIの画像解析で判別し、天然ゴムの生産性向上に取り組んでいる。

中川氏によると「この技術のコアは、農園スタッフが持つ病害判断の暗黙知とAI技術の融合」にある。これにより、スタッフの熟練度に依存しない診断やその精度向上が期待できるほか、山手線内側の3~4倍もの面積がある自社農園で効率的な罹病木の発見が可能になったそうだ。現在は自社農園でのトライアルを継続しているが、将来的には外部農園への展開も検討するという。
また、パラゴムノキの農園管理技術も“拡充”の取り組みの一つ。過去30~40年ほど自社農園で収集してきた収量や品種をはじめとする大量のデータを活用し、長期の植林計画を作る独自システムを開発した。
いつ、どこに、どういった品種を植えれば良いのか――システムが導き出した植林計画によって天然ゴム収量の平準化、さらに向上が期待できるそうだ。また、単に生産性の高い品種を植えることで収量の向上を図れるものの、同時に病害リスクが上がることも考えられる。そのため独自システムでは、考慮すべき病害リスクなど様々な制約条件も織り込んだことがポイントだという。
大月氏は「AIが発展したからこそ当社のデータを強みとして活かせるようになり、植林計画システムにまで発展できた」と話す。今後、同技術も天然ゴムのスモールホルダー(小規模農家)への展開を目指す方針で、「天然ゴムの生産量増加やスモールホルダーの事業に貢献していきたい」と展望を示していた。
新たな供給源の確保へ
“多様化”の取り組みの中心はグアユールだ。これは米国南西部からメキシコ北部が原産の低木で、天然ゴムの新たな供給源として有望視されている。天然ゴム成分を作る植物の中でも乾燥地帯で育つことから、水ストレスの低減や砂漠の緑化などに貢献できる可能性もあるため、同社の研究対象に選ばれたそうだ。
グアユールから天然ゴムを得るには、樹液を凝固、乾燥させるパラゴムノキとは全く異なり、植物体の粉砕や成分の抽出、不純物除去など複雑な工程が必要となる。同社ではこうした天然ゴムの抽出技術をはじめ、栽培やタイヤへの適用技術まで一貫した研究開発を実施。2015年にはグアユールを用いたタイヤを完成させ、一連のプロセスは完成済みだという。ただ、個々のグアユールの生育やゴム含有量にばらつきがあり、その均一化や優秀な品種の増殖が課題になっていた。

そこで、同社は高精度な遺伝子解析技術を持つイスラエル企業のNRGeneと協力し、優良品種の選抜をスタートした。さらに、選抜品種はキリンホールディングスが有する植物の大量増殖技術を活用して増殖。中川氏は「当社と2社の技術を組み合わせることで安定した高生産の実現を加速できる」と期待する。
米国の自社農園では、大量増殖技術を適用した苗のモニタリングを3年ほど実施しており、現在のところ順調に育成し、見込んでいた収量が確認できているそうだ。2020年代の商業化の実現には生産性の向上と品質の安定性が重要で、今後も優良品種の選抜を繰り返し、より生産性の高い品種の育成に取り組む方針だ。
ブリヂストンでは、グアユール由来の天然ゴムの用途についても検討を重ねている。例えば、グアユールの天然ゴムでもパラゴムノキ由来のものとほぼ変わらない特性が得られることから、丈夫さが求められるトラック・バス用タイヤへの応用が考えられているそうだ。米国で生産した天然ゴムから米国市場向けのタイヤが製造できれば、地産地消も実現できる。
さらに、グアユールの天然ゴムはパラゴムノキと比較してタンパク質の含有量が少ない特徴があり、アレルギー反応を引き起こしにくいゴム手袋を実現できる可能性もあるという。大月氏は「最もお客様に価値を提供できるビジネスを見定めていきたい」と抱負を述べていた。
ブリヂストンのマイルストン2030では、「再生資源または再生可能資源に由来する原材料の比率を40%に向上する」という目標を掲げており、再生可能資源である天然ゴムは重要な役割を担っていく。タイヤ開発という観点でも、耐久性などの面で基盤となり続ける欠かせない原材料だ。
中川氏は「天然ゴムの技術を展開していくことが社会価値、顧客価値への貢献に繋がっていく――このビジョンを持ちながら、今後も研究開発に取り組みたい」と意気込みを示す。持続的な価値の提供を目指すブリヂストンの取り組みにこれからも注目していきたい。
天然ゴムの代替となる合成ゴムを開発
ブリヂストンでは、天然ゴムの代替となる合成ゴムの研究開発も進めている。天然ゴムと一般的なIR(ポリイソプレンゴム)を比較すると、前者の分子構造がシス率100%であるのに対し後者はシス率94~98%程度となるが、同社はより天然ゴムに近いシス率の新規IRを実現している。
シス率の高さはゴムの強度を示す数値とも言えるため、天然ゴムの代替を開発するにはこのシス率をいかに高められるかがポイントだ。同社では、独自の触媒技術を活用することで限りなく100%に近いシス率を達成したという。現在、この触媒の知見を活かしたIRの合成技術は量産化に向けた検討段階だ。
また、合成ゴムの研究でもサステナブル化に力を入れる。大月氏は、「これまでIRの原料であるイソプレンは石油由来だったが、植物原料由来のイソプレンを用いることが可能になれば、タイヤに使用するゴムをバイオ素材に転換できる」と見通しを示す。
その他、合成ゴムのリサイクル技術や、タイヤ補強繊維におけるリサイクル繊維もしくはバイオ素材の活用、米のもみ殻シリカの採用なども進めることで、環境長期目標の「100%サステナブルマテリアル化」達成を目指す。あわせて、より丈夫なゴムの開発によってタイヤ材料の使用量削減にも取り組み、事業のサステナブル化を一気に推進していく考えだ。