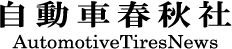大型車の車輪脱落防止に向けて
大型車の車輪脱落防止に向けて、タイヤ業界を挙げて取り組みを進めているさなか。そのために求められるのは日頃からの点検・整備、そして適切な使用である。中でも「締め付け方式の確認と規定トルクで確実な締め付け」「増し締めの実施」「運行前の点検」「ホイールに適合したボルト・ナットの使用」――この4点が車輪脱落事故防止のポイントとなる。特に大型車ホイールには3つの方式が混在しているため、より一層の注意が必要だ。事故の未然防止をいかに図るか。国土交通省自動車局整備課の板崎龍介課長に、「締め付け方式の確認と確実な締め付け」にフォーカスし話を聞いた。
――大型車のホイールには現在、JIS方式、従来・ISO方式、そして6年前に導入された新・ISO方式の3種があり、市場ではそれらが混在しています。それぞれに互換性がなく締め付け方式が異なるため、各方式に合った締め付けを行わなければなりません。その確認を怠ると、重大な事故につながる可能性が高まります。そもそもなぜ新・ISO方式が導入されたのでしょうか。

「2004年に大型車のホイールボルト折損による車輪脱落で歩行者が死亡するという痛ましい事故が起きました。社会問題化したこの事故を契機として、車両の側で事故防止を図ることができないか、検討してきました。
大型車市場では国産車が大勢を占めており、それにはJIS方式が採用されています。このJIS方式はたとえば、内輪タイヤの点検がしにくいなどと指摘されていました。一方、輸入大型車に採用されている従来・ISO方式は構造がシンプルなのでタイヤ交換や点検・整備が容易、締め付け方式が単純であり、長く使ってもボルトやナットの傷みが少ないなどの特徴があります。
JIS方式とISO方式とではそれぞれメリット・デメリットがあり単純な比較はできません。ですが、中長期的な視野、また国際的な調和という観点から考え、より整備のしやすい方法はどちらかということから、ISO方式のほうへ舵が切られたのです。
ただ、ハブ周りの設計等が異なりますので、すべての大型車のホイール方式を一斉に切り替えるということは不可能です。そこで大型車メーカーでは、2009年10月から適用が開始となる排出ガス規制・ポスト新長期規制に適合する新車からこの新・ISO方式を採用し、以降、順次採用の拡大を図っているところです」
新・ISOホイールは約2割に
――2009年から大型車に新・ISO方式ホイールが採用され始め、現在で6年が経過しました。大型車市場において、新・ISO方式ホイールがどれくらい普及していると見ているのでしょうか。
「社会情勢が変化している中、国産の大型車メーカーでは着実にそれへの切り替えが進められていると認識しています。今の時点で新・ISO方式採用の車両は市場のおよそ2割を占めているものと見られています。今後も現在のペースで進捗していくのではないでしょうか。従って、当面の間は大型車市場においてJIS、従来・ISO、新・ISO、この3種の方式のホイールが混在します」
――JIS方式は球面座で締め付ける、新・ISO方式は平面座で締め付けると、締め付け方式が異なります。また、19.5インチのホイールの場合、ボルト穴がJIS方式と新・ISO方式ともに8穴と同じですが、PCDが異なるため、ボルトに対してホイール穴が合いません。さらに新・ISO方式の場合、左車輪の場合も右ねじと、これもJIS方式とは異なります。3種の方式のホイールが混在することで、作業者のヒューマンエラーによって新・ISO方式とJIS方式との誤装着が生じる危険性が指摘されますが。
「これまでのところ、新・ISO方式とJIS方式とを誤って組み付けたという事例の報告は聞いておりません。ただ、大型車市場で今後、新・ISO方式採用が増えてきますから、それによって誤装着が増える可能性は考えられます。また、ヒューマンエラーは慣れや漫然と作業を行うことでも生じますので、やはり常に注意を払って作業に取り組むことが求められます。