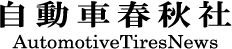更生タイヤ全国協議会(更タ全協)はこのほど、24年度リトレッドタイヤ生産実態調査をまとめた。同調査によるTBリトレッド比率は19.9ポイントで、前年実績20.0ポイント比ほぼ横ばいを示した。リトレッドタイヤの年間生産量は136万3千本で、前年より1万6千本減、対前年同期比1.2%減だった。
これまで運行三費の経費削減の側面でスポットを浴びることが多かったリトレッドタイヤ。しかし、社会では環境対応の観点からサステナビリティへの取り組みが重視されるようになった。
リトレッドタイヤはコスト削減ばかりではなく、使用原材料の削減による資源効率の向上やCO2排出量の削減に貢献する。その注目度が増すにつれ、日本国内市場での需要は徐々に伸長してきている。
更タ全協まとめによるTBリトレッド比率は、トラック・バス(TB)用のリトレッドタイヤ販売本数を国内販売本数(新品本数+リトレッドタイヤ本数の合計)で割り、その数値×100で算出される。
24年度はTB新品505万6千本(前年比1.0%減)、TBリトレッド125万3千本(同1.6%減)と、ともに前年実績に届かなかった。新品+リトレッドの合計は630万9千本、TBリトレッド比率19.9ポイントを示した。
TBリトレッド比率は18年から22年まで18ポイント前後で推移してきていた。しかし23年は新品が前年比8.3%減少したのに対し、リトレッドは前年比3.9%増加。TBリトレッド比率は20%台へと達した。24年もほぼ同水準で推移した。
リトレッドタイヤ全体と品種ごとの生産本数は〈表〉の通り。
メインとなるTBリトレッドは、夏冬合計で11R22.5サイズが前年比4.5%減少した。だが偏平サイズ同1.5%増、4トンサイズ0.4%増、その他サイズ2.2%増と、いずれも前年実績を上回った。
TBリトレッドの冬タイヤで11R22.5が同10.8%減、偏平サイズで同4・1%減と前年実績を割り込んだ。更タ全協では「履きつぶしが増えたこと」を要因としてあげる。需要業界での燃料費高騰に加え、ドライバー不足に対応するための人件費増、車両の稼働率減などの問題が根底に潜んでいそうだ。
ただ、リトレッドタイヤは、環境志向の高まりを受け生産量は今後も安定的に推移するものとみられる。23年の国内市場すべての販売タイヤが新品だった場合と比べたCO2削減量(原材料生産/原材料輸送/タイヤ生産/廃棄・リサイクル各ライフサイクルの合計)は年間22万1千トン。275/80R22.5サイズ換算で、新品タイヤ約121万本を生産する際のCO2排出量に相当する(いずれもJATMAによる算定)。
業界調べによると、米国市場ではリトレッドタイヤ率は50%を超えており、ドイツ市場でも半数に迫る。そのような海外市場と比べると、国内市場のそれはまだ低い。
リトレッドタイヤの使用が増えると、CO2排出量や使用資源量の削減への貢献が拡大する。今後、リトレッド比率が高まることで、サステナブル社会の実現に向けての貢献が期待される。
このようなことを背景に、更タ全協は25年度の展望を「リトレッド比率は20%程度を維持し推移するのではないか」と見通す。なかでも22年度以降、量的に拡大を続けるTB偏平サイズやLTサイズでさらなる成長が期待される。