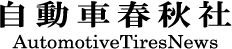4月7日「タイヤゲージの日」
(前編からのつづき)

「『基準』を守るためには、それ自身の精度が正確でなければならない」、このように話すのは旭産業(東京都大田区)の石田明義社長=写真上=。旭産業はタイヤゲージの老舗専門メーカーである。
JATMAが先に明らかにした、24年1月から12月に全国で実測した路上タイヤ点検の整備不良率は49.4%。町を走るクルマの2台に1台はタイヤになんらかの整備不良があるという勘定だ。その項目別ワースト1位は「空気圧不足」で不良率44.5%にものぼった。
タイヤの日常管理の重要性を訴求するため、業界をあげて推し進めるのが「4月8日 タイヤの日」の活動だ。ここで冒頭の石田社長の指摘につながる。「タイヤ点検で使用するタイヤゲージ(エアゲージ)の精度について、もっと関心を持っていただきたい」。
そのような観点から、同社では前日にあたる4月7日を「タイヤゲージの日」として制定。その認知度向上に努めている。
タイヤゲージはその姿・形から、ついレンチのような工具の1種として見られがち。しかし、実際は精密な部品がいくつも組み合わされた検査・測定機器である。経年劣化で徐々に精度誤差が生じるのはやむを得ない。ただ修理や校正のため、同社に回収された製品を分解し検品すると、ピット床面への落下などの衝撃で本体や部品に影響していたケースが非常に多いという。
また、「コンプレッサーの配管が改善され、最近では少なくなってきた」と前置きするものの、ドレン管理が不十分で、ゲージ内の部品に錆が生じていたケースが現在も散見されるそうだ。
石田社長は「適正なタイヤ空気圧管理の大前提として、タイヤゲージの精度が正確でなければならない」と述べる。「日ごろの体調管理と同様で、お使いのタイヤゲージに少しでも違和感を覚えることがあれば、すぐにご相談いただきたい」、このように提案する。
精度チェッカーなどサポートツールも

旭産業はタイヤゲージを使用する作業に際し、それをサポートするツールも開発。タイヤゲージの精度誤差を簡単にチェックすることができる精度チェッカー「SC-70」やデジタル・マスターゲージ「DEM-90」をラインアップ。タイヤゲージの落下防止として強力なマグネットを採用したゲージホルダー「AG-HLD」といった便利ツールも販売展開する。
近年、取り組みを強化しているのが、タイヤゲージそのものの進化。部品をアップデートし測定精度の向上を実現した。ハンドルレバーの形状改良も行った=写真下・右が現モデル、左は旧モデル=。長さを延長し角度つけることと軽量化することで、レバーを握る力を従来品に比べ半減させた。目盛り板も人間工学に基づく新デザインとし視認性を向上した。
石田社長は「女性整備士の声をフィードバックし開発した。それまで当たり前だと思っていたことでも、現場に新しい〈気づき〉がある。メーカーとしてこれからも使いやすく、測定精度の高い製品を開発していくことが使命」と語った。