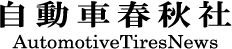日本自動車工業会(自工会)は19日、3月度記者会見を開催した。

片山正則会長(いすゞ自動車)=写真上=は、米国の通商政策への対応、適正取引の浸透、未来志向の型式指定制度などについて、自工会の考えかたを説明した。
そのなかで、対米国通商政策については「日本の自動車メーカーは1982年から米での現地生産を開始し、部品の現地調達を積極的に進め米国企業の一員として継続雇用と投資を促進した」と指摘。23年までに616億ドルの累計投資額、現地生産台数年間320万台など数値を示し米国経済への貢献度を強調した。
「ピーク時から大幅に減少したが、日本にとってアメリカは引き続き自動車輸出額6兆円、自動車総輸出の約3割を占める第一の輸出先。開かれた貿易体制の維持は、550万人の日本の自動車産業にとって極めて重要」とし、トランプ政権が検討している25%の追加関税への懸念を示す。日本政府へは追加関税の適用除外に向けた尽力、米国政府へは日本の自動車メーカーが安心して投資できる政策とビジネス環境の整備を期待していると述べ、さらに追加関税が実施された場合の生産調整の可能性について言及した。
「仮に追加関税となればかなりの生産調整が予測される。短期的なショックをどう吸収するか。次善の策を官民でできることを中心に経済産業省とも協議した」と、官民の連携を強調した。
適正取引の浸透に向けては、日本のモノづくりの競争力確保と健全な取引環境の構築を両輪とする考え。サプライチェーン全体への理解をはかるべく、パートナーシップ構築宣言の拡大への取り組みや、サプライヤー集積地でのセミナー開催など業界が一丸となって浸透に努めていく。自工会では自主行動計画を改定し、量産終了後の型保管費用など必要な支払いを明記し適正化に取り組む方針を示した。
型式指定問題では、国土交通省の「自動車の型式指定に関わる不正行為の防止に向けた検討会」の取りまとめを踏まえ対応する。
片山会長は「国際的な競争力向上をめざした制度・仕組みづくりは昨今の技術進歩速度を鑑み、待ったなしの状態。将来のデジタル時代に即した新技術に対応する認証制度のありかたを未来志向で検討に着手していきたい」と、今後の方針を述べた。

また同日、副会長に設楽元文氏(ヤマハ発動機)=写真下=が就任した。二輪車委員会、自工会が掲げる7つの課題のうち「競争力のあるクリーンエネルギー」「業界を跨いだデータ連携」を担当する。