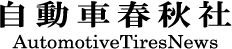モータージャーナリスト瀬在さんと、ランフラットタイヤ装着車に乗りながら
BMW M850i xDriveクーペ
ノーマル構造と遜色ない性能を実現
最新ランフラットタイヤが描く未来

BMW M850i xDrive クーペはV型8気筒DOHCエンジンを搭載した総排気量4.4リットルのガソリン車。最高出力530PS/5500rpm、最大トルク750Nm/1800rpm−4600rpmという超ハイパワーのスポーツカー。内燃機関車ながら車両重量はFCEVのトヨタMIRAIとほぼ同じ約2トン。ランフラットタイヤを標準装着している。BMWはランフラットタイヤを積極的に新車承認するカーメーカーだ。今回はランフラットタイヤのこれまでの系譜をたどりつつ、現在のその性能を体感する
ランフラットタイヤ
定義と成り立ち

「トーク・アバウト・ドライビング」シリーズで「前後異サイズのタイヤ装着車」として、スカイラインGT NISMOに試乗した。このクルマは、ベースとなるスカイライン 400RをNISMOがチューンアップし、よりハイパワー化したもの。その開発に際してNISMOは装着タイヤを前後輪同サイズから前後異サイズへと変更したのだが、同時にタイヤの構造をランフラットからノーマル(非ランフラット)へと変えていた。
その意図について、NISMOは「タイヤをノンランフラット専用に開発した構造により、しなやかな乗り味とバネ下重量の軽量化を実現」と言及する。ロングツーリングで重視される〈速く〉〈気持ち良く〉といった上質な走りを実現するための選択とみてとれる。
なお、ランフラットタイヤとは、タイヤの空気圧がゼロになっても一定の速度で一定の距離を走行することができるタイヤ。ISO技術基準では、タイヤ空気圧0kPa時に時速80キロで距離80km走行可能と定められている。

1987年、スコットランドの獣医師であるジョン・ボイド・ダンロップがゴムの内部に空気を入れる自転車用空気入りタイヤ(Pneumatic tire=ニューマティックタイヤ)の実用化に成功した。その1年後、フランスのミシュラン兄弟が取り外しの利く空気入りタイヤ『デモンターブル』を発明した。使用中にパンクして空気が漏れたとしてもタイヤを取り外し穴を塞ぎ修繕することで再びその内部に空気を入れ保つことが可能となった。
それまでのソリッドタイヤや輪縁に鉄をはめた車輪と比べ、ニューマティックタイヤは1本当たりのタイヤ重量を飛躍的に軽くした。それにより走行速度がアップし、操縦性と乗り心地が劇的に向上した。このとき以来、タイヤと空気は切っても切れない関係となった。内部の空気を保持できなければ期待するタイヤ性能は得られない。タイヤ内の空気は徐々に抜けていき、偶発的・突発的に空気圧がゼロになりうる。ランフラットタイヤとはそんな宿命に対し知恵と工夫をこらし挑み続けてきた解決策のひとつだ。
中子式 シール剤
サイド補強式

ランフラットタイヤの歴史を振り返ると、その性能を実現するアプローチとして、構造上からいくつかに分類することができる。
ひとつは中子式ランフラットタイヤ。タイヤ内部にあらかじめ金属製リングを仕込んでおき、パンクしタイヤ空気圧がゼロになってもそのリングが荷重を支えることで走行することを可能とするもの。標準リムを使うコンチネンタルタイヤの「コンチサポートリング」と、特殊リムを使うミシュランの「PAXシステム」がとくにその名を馳せた。
前者の技術開発にはのちにブリヂストンと横浜ゴムが、後者にはグッドイヤー、ピレリ、住友ゴム工業(ダンロップ)、TOYO TIRE(当時の社名は東洋ゴム工業)が加わった。中子式タイプの技術開発と市場展開に向け業界がまるでビデオのベータ方式とVHS方式の陣営に二分されたように、それぞれのグループが覇を競うような形となった。
もうひとつはシーラントタイヤ。タイヤの内部にゲル状のシーラント剤を塗布、あるいは封入するもの。トレッド面に穴が空いたときにシーラント剤が塞いで硬化し、それ以上の空気漏れを防ぐという仕組み。ガレ場など荒れた路面を走行するシーンの多いラリー競技車から採用が始まったと言われる。コンチネンタルタイヤの「コンチシール」はその代表的な技術。
シーラント剤を活用したタイプにはもうひとつ、70年代に欧州のダンロップ(当時)が開発した「デノボ」がある。ホイールにシーラント剤を含んだカートリッジをセットしたものだ。タイヤがパンクしその内面がカートリッジと接触するとシーラント剤が噴き出してパンクを修理するもの。その後、パンク時のホイールリム外れを防止する「デンロックシステム」を兼ね備えた「デノボ2」へと進化した。
この「デノボ」「デノボ2」に、タイヤサイド部のゴムを肉厚にしリムから外れにくくする「サイド補強ゴム」構造が採用された。現在主流のサイド補強式ランフラットタイヤの原形がそこにある。
サイド補強式ランフラットタイヤは80年代後半、その仕様がポルシェ959に標準装着され脚光を浴びた。当時のブリヂストンの発表によると、もともと同社のランフラットテクノロジーは80年代前半に身障者用車両向けに考えられたもので、空気圧が失われた状態でも安全な場所まで走行可能なタイヤとして開発したという。
一時は中子式タイプがランフラットタイヤのグローバルスタンダードになるとみられていた。だがランフラット走行時の振動問題。高性能車に装着されるタイヤで超偏平化が進む傾向にあるなか偏平率の低いタイヤではそれを採用することがむずかしいという構造上の課題。とくに「PAXシステム」は専用ホイールとの一体型のため汎用性が低くタイヤ交換時の扱いが容易ではないこと。これら複合的な理由から、市場で普及するには至らなかった。
現在は「コンバットタイヤ」や「防弾タイヤ」と呼ばれる、戦闘地域や未整地での走行が多い軍用車、要人が利用するVIP車、あるいは新交通システムなどでの採用にとどまっているようだ。
サイド補強式ランフラットタイヤは2000年代頃から、北米市場や欧州市場の高性能車に標準装着されるようになった。当初はタイヤサイド部を補強するため、どうしても乗り心地がかたくなり、コーナリング時のハンドリング性能にその影響が及ぶと指摘する声が多かった。
しかしその後、改良が進み、タイヤのプロファイル形状やビード部の構造、材料技術は大きく進化。現在はノーマルタイヤと同等、またはそれ以上の乗り心地と操縦性を実現したという。
BMWが承認する
★(スター)マーク

BMW M850i xDrive クーペにはサイド補強式ランフラットタイヤが純正装着されていた。試乗した車両にはピレリ「P ZERO RUN FLAT」で、タイヤサイズはフロント245/35R20 95Y XL(ホイール8J×20)、リア275/30R20 97Y XL(ホイール9J×20)。
タイヤのサイドウォールには★(スター)マークが刻印されている。これはこのタイヤがBMWのために専用開発された承認タイヤであることを示す記号。BMW承認タイヤは車両のサスペンションと一体で共同開発することでDSCやABSなどのセーフティシステムと最適な組み合わせとなり、ステアリングレスポンスや快適性などの性能がその基準を満たしたものを表す。

車両にはタイヤ空気圧コントロール(TPMS)機能が備えられている。ドライバーが車内で常に、タイヤの空気圧や内部温度を視認することができるものだ。ランフラットタイヤは空気圧ゼロでも走行可能なので、TPMS機能がないと、運転手がパンクしたことに気付かずそのまま走り続けてしまわないとも限らない。それを未然に防ぐためだ。
瀬在さんがBMW M850i xDriveクーペを駆る。高速道路でのドライブフィールを聞くと、「ノーマルタイヤと比べると少しかたい気もしますが、それでも過去のランフラットタイヤよりは格段に乗り心地が良くなっています」と印象を語る。「サーキット走行ではないので、高速コーナリング性能を試すことはできませんが、思い描くラインのとおりにトレースしますし、前後方向のグリップはスポーツタイヤらしい安定した直進性能を発揮しています」、このように続ける。

ハーシュネス(舗装路の継ぎ目などの突起を通過したときに生じる振動や音)も、ランフラットタイヤはノーマルタイヤよりもエンベロープ性(衝撃を吸収する性能)で不利と言われる。だが、BMW M850i xDriveクーペ装着のP ZERO RUN FLATは「スポーツ性能とコンフォート性能を高次元で両立するというむずかしい技術テーマをしっかりとクリアしたと思います」と、瀬在さんは評価する。BMW承認マーク取得の証(あかし)をそこにみる。
タイヤの技術進化はとどまることがないというのを、瀬在さんのコメントからうかがい知る。
CASE進展で
高まる存在意義
EVやFCEVは車両重量が内燃機関車よりも重くなる。道路への負荷や燃費(電費)の影響を考えると、タイヤにはより一層の軽量化が求められる。ランフラットタイヤは構造上、ノーマルタイヤよりもそれはむずかしい。CASEが進むこれからの時代に、ランフラットタイヤでそれをどうクリアするか、重要なテーマだ。
ただ、CASEが進むからこそ、ランフラットタイヤの存在意義は一層高まるのはまぎれもない事実だ。クルマの自動運転技術のレベルが上がるにつれ、走行中の安全を担保するタイヤにはランフラット性能が求められる。またカーシェアリングのように、クルマを所有する人や事業者と使う人とが異なる場合、ノーマルタイヤよりもランフラットタイヤのほうが利便性はより高い。
CASEの時代にふさわしい性能へと、ランフラットタイヤはさらに進化を続けるに違いない。
=瀬在仁志(せざい ひとし)さんのプロフィール=

モータージャーナリスト。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員で、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員のメンバー。レースドライバーを目指し学生時代からモータースポーツ活動に打ち込む。スーパー耐久ではランサーエボリューションⅧで優勝経験を持つ。国内レースシーンだけでなく、海外での活動も豊富。海外メーカー車のテストドライブ経験は数知れない。レース実戦に裏打ちされたドライビングテクニックと深い知見によるインプレッションに定評がある。