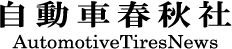EVタイヤに求められる2大特性、静粛性と省電費

前回のホンダeに続いて、今回も国産BEV(バッテリー式電気自動車)をピックアップした。日産LEAF(リーフ)。日本メーカーの本格量産BEVの草分け的存在だ。2010年に初代モデルの販売が開始された。17年にフルモデルチェンジされ現在の2代目が登場した。
BEVは今や、米国のテスラと中国の比亜迪(BYD)の2強とそれ以外、という勢力分布図になりそうな気配が漂う。24年7月から9月のBEVの世界販売台数は、前者が約46万3千台で首位をキープしたが、後者が約44万3千台とかなりの勢いで迫ってきてきた。BEVだけでなくPHEV(プラグインハイブリッド車)を合わせると、BYDがテスラを大きく上回り、すでに世界トップの座に就いている。
テスラとBYDが世界を舞台に苛烈な競争を繰り広げているなか、では日産リーフの販売台数はどれくらいなのだろうか。瀬在さんにメーカーに確認してもらったところ、24年9月末時点で初代(2010年)からのグローバル累計販売台数は69万1300台という回答だった。2強に大きく水をあけられている。

クルマは世界市場でCASEが進展する。なかでも欧州はいち早くパワートレインの脱ICE(内燃機関)を宣言。ドイツでは2035年、フランスやスペインでは40年までにガソリン車・ディーゼル車に加えハイブリッド車、やがてはPHEVさえも新車販売の禁止をめざすなどEV化へと大きく舵を切った。その流れに、膝元である欧州カーメーカー(欧州製EV)が乗るかと思われたが、現実はスタートアップ企業だったテスラが急速に伸長し市場を席巻したのはもはやだれもが知るところだ。
米政権のEVへのシフト減速施策、欧州の中国製EVに対する関税引き上げ検討など、EVの普及に逆風が強まりつつあるのは確か。だが、多少の紆余曲折はあるとしても、脱ICEの実現にはEVやFCEV(燃料電池車)しか道はない。そういう意味では日本(自工会)が標榜する「マルチパスウェイ」は正しい解(かい)。ただ、低価格を武器にした中国製EVがこれほど早く、ここまで大きく市場を占めるようになったのは想定外だったのかもしれない。

さて、リーフである。17年に登場した2代目はその後、数度にわたり一部の仕様向上が行われた。フルモデルチェンジ時に、搭載の駆動用バッテリー容量を初代24kWhだったものから40kWhへとアップ。19年には62kWhの大容量リチウムイオン電池を搭載したリーフe+(プラス)をラインアップに加えた。航続距離もWLTCモードで458kmへと伸ばした。22年のマイナーチェンジでは40kWh搭載車・60kWh搭載車へとアップデートされた。
全長4480ミリ×全幅1790ミリ×全高1560ミリ(e+は1565ミリ)、ホイールベース2700ミリ。車重はグレードにより1.5トン強から1.7トン弱。本シリーズ「プジョー308 GT HYBRID」の回で触れたが、欧州での分類方法ではCセグメントの5ドアハッチバック車。そこで忘れてはならないのが、リーフは5人乗りの登録車として世界初のBEVということだ。

今回試乗したリーフe+ Xグレードには、ダンロップの「ENASAVE(エナセーブ) EC300」215/50R17 91Vが装着されていた。「エナセーブ」シリーズは、タイヤの転がり抵抗を低減し燃費性能を向上しながら、背反するウェット性能を両立。乗り心地や静粛性など基本性能を高次元でバランスしたスタンダード低燃費タイヤである。
「2代目リーフは初代と比べると大変ブラッシュアップされています。車重の重さにサスペンションが対応しきれずボコボコと跳ねるような感覚があった初代に対し、フルモデルチェンジに際してしっかりと改善し、2代目はすっきりとした乗り味となっています」と瀬在さんは話す。
「装着されたこのタイヤは路面のインフォメーションをきっちりと伝えてくれるので運転していて安心感がありますね。リーフはモーター音があまりしないので静粛性はタイヤに特に強く求められるところです。これは道路の継ぎ目や段差をマイルドに包み込むので、リーフによく合っています」とし、その評価は高い。
中速から高速域へと一気に加速する。EVらしいトルクフルな走りをみせるリーフ。瀬在さんは「レスポンスは決して悪くありませんが、スポーツタイヤとエコタイヤとでは感触が異なって当然でしょうね」という印象を語ってくれた。
「クルマの前席がアップライトなつくりで、インパネやダッシュボード周りも地味。百花繚乱の様相をみせる、新興メーカーのEVと比べると古くさく感じられるかもしれません。ですが、このリーフの技術がベースとなりクロスオーバーEVのARIYA(アリア)や軽EVのサクラという人気車種に受け継がれています。それに大事なことは、発売から10年以上経過した今もバッテリー火災の事故は1件も報告されていません。日本製EVの価値は信頼性や安全性の高さにあると言って過言ではないと思います」
日本のクルマづくりの思想はICEにしてもBEVでも共通しブレがない。
=瀬在仁志(せざい ひとし)さんのプロフィール=

モータージャーナリスト。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員で、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員のメンバー。レースドライバーを目指し学生時代からモータースポーツ活動に打ち込む。スーパー耐久ではランサーエボリューションⅧで優勝経験を持つ。国内レースシーンだけでなく、海外での活動も豊富。海外メーカー車のテストドライブ経験は数知れない。レース実戦に裏打ちされたドライビングテクニックと深い知見によるインプレッションに定評がある。