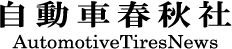現場主義のDXでタイヤ保管に新たな価値を。AIの活用にも本腰
タイヤ保管サービス「タイヤパークWeb管理システム」を展開する中央海産株式会社。海産物卸を祖業とし、現在は倉庫業を展開。倉庫業の一環として始めたタイヤ保管サービスだが、現在は同社の主力事業に成長。現場の知見を踏まえたDX化を進めタイヤ保管にとどまらない価値を創出する。直近で取り組むのがAI活用。これによって保管から測定、そして情報活用ビジネスまで拡張していこうという戦略だ。
きっかけはディーラー。システム携え全国展開
同社がタイヤパークWeb管理システムを始めたのは05年。きっかけとなったのは知り合いの国内大手ディーラー店長からの「タイヤを保管してもらうことはできないか」という一言だった。
中央海産は海産物卸を祖業にしていたことから、冷凍・冷蔵・常温いずれの倉庫も所有。倉庫業へ事業転換してからも食品の保管をメインにしてきた。そこに「タイヤ」というオーダーが舞い込んできたわけだ。
「知己のディーラー店長からの依頼で受けたが、調べていくとタイヤ保管ビジネスの課題が浮かび上がってきた」。こう語るのは、田中文敏社長だ。
田中社長によると、事業を始めた05年当時は預かったタイヤを店舗の敷地内に保管するケースが散見されたという。自社の所有物を敷地内に保管することは問題ないが、顧客からの預かりタイヤを保管する場合は有償・無償にかかわらず、倉庫業法の許認可(現:登録申請)を得て営業倉庫に保管しなければならない。
この状況に着目した田中社長は「保管サービスを始めたい業者と倉庫業者を『タイヤパーク』がハブになってつなげていくことで、双方がウィンウィンになれるのではないか」、そう考えた。自社倉庫でのタイヤ保管を拡大していくとともに他県の倉庫事業者にも声をかけ、タイヤパークの〈ネットワーク〉を広げる。10年に長野県の倉庫業者と提携し初の県外進出を果たした。現在までに30都府県へとネットワークを広げている。
並行して進めたのが、システム開発だ。その中核となる「タイヤカルテ」は、タイヤの画像や残溝などの状態をウェブ上で管理。ユーザーもスマホなどからタイヤの状態を確認することができる。タイヤごとに「良好」「要経過観察」「早期交換推奨」の3つで評価され、「要経過観察」となれば2~3カ月以内の交換、「早期交換推奨」の場合は早期の交換を勧める。
このような情報はディーラーにも共有される。ディーラーが顧客のタイヤ状態を把握することで、来店前に新品タイヤへの交換を勧め、事前に組み換えをすることでスムーズな商談を行えるのだ。
保管する倉庫業者側へのサポートも確立する。そのひとつが「タイヤカルテマイスター認定」だ。これは同社独自の認定制度で、提携倉庫事業者が残溝等のタイヤ情報の測定・取得業務を請け負う場合には認定取得を必須とする。国内大手タイヤメーカーの代理店で40年務めた人物が講師を担い、提携の倉庫事業者に安全や販促につながる点検箇所について研修を行っている。
タイヤプロファイラーとは。AIで種類・状態を判定

システム開発で、新たな動きを見せる。それがタイヤ自動検品装置「タイヤプロファイラー」だ。
倉庫に入庫されるタイヤをタイヤプロファイラーの台の上に置くと、約2秒でタイヤの写真を撮影。この2秒で検品を済ませるとともに、撮影した画像からタイヤの状態診断をAIが行う。現在は残溝を測定することができ、タイヤのメーカーや品名、サイズ、製造年週なども判別する。将来的にはタイヤプロファイラーで残溝以外の劣化状況も診断できるようにしたい考え。
そこで現在、AIに学習させているのがクラック(タイヤのひび割れ)だ。開発担当者によると、「AIが認識する際に、クラックなのか汚れなのかの判別がむずかしい」と話す。実装するためには大量のクラックのケースを学習させ精度を高めなければならない。そのためには最低でも1万枚のクラックのケースを学習させる必要があるという。
これによってタイヤの状態を診断できれば、大幅な業務効率化につながる。これまでは倉庫作業の一環で残溝や状態の確認を行っていたが、それが軽減される。タイヤの状態はタイヤカルテに反映され、ディーラーや販売店は販売促進につなげることができる。
タイヤプロファイラーは自社ですでに稼働を開始し、関西エリアの倉庫事業者でも稼働させた。近い将来には全国の事業者への展開を目指す。
エンジニアは自社で用意。現場主義のDXチームも

ニーズを聞きとり、それを機能改善や新しいサービス開発に生かす――この姿勢が「タイヤカルテ」や「タイヤプロファイラー」「タイヤカルテマイスター認定」などにつながってきた。
実は、こういったサービスを支える機器やシステム開発のほとんどを内製化している。その理由について風間正利執行役員は「現場の知見を開発に生かすには自前でエンジニアを抱えることが最適。外注する場合にも現場と開発の両面で外注先に的確に指示することが可能だから」と説明する。
こうしたタイヤ保管のDX化に向けた人材戦略は新しいステージに進む。それが若手社員を中心とした「DXチーム」の結成だ。チームは新卒入社した若手の数名で構成。将来的にはエンジニアとしての活躍を予定するが、入社後2年間は倉庫業務に従事する。ねらいは「現場主義のDX」を進めるためだ。風間氏は次のように話す。
「現場を知らずにDX化を進めようとすると、現場との間に深い溝が生じかねない。これを避けるためには現場業務を理解した社員がDXを担当するのが望ましい。中長期的な施策となるが、現場とDX双方の知見を兼ね備えた人材育成を進めていきたい」
実際にタイヤプロファイラーを開発するにあたっても、現場業務の知見が生かされた。ハードウェアチームの勝村和重リーダーもそのひとり。勝村氏は実際に倉庫業務を体験した上で、「測定の時間ひとつとっても、繁忙期に倉庫業務をスムーズに進めていくためには重要だ」と強調する。
タイヤプロファイラーの測定時間は1本のタイヤに対して約2秒。これ以上遅ければ倉庫業務に支障が出るが、これ以上早くしても「機械のボタンの押し間違えなど、ヒューマンエラーが発生しかねない」という。現場の知見を生かさないと「業務効率化のため」と謳うDXが効率化を妨げかねないのだ。
このような現場で培われた知見や顧客からのニーズをシステム開発のなかに組み込み最適化していく。これが今後のミッションとなる。
田中社長は「現場の知見や提携する倉庫事業者やディーラーからの声、さらにタイヤメーカーなどさまざまな人から意見をお聞きし、より利便性の高いサービスにしていきたい」と意欲を示す。最初のきっかけとなったタイヤ保管から20年、きょうもサービスは進化しつづけている。